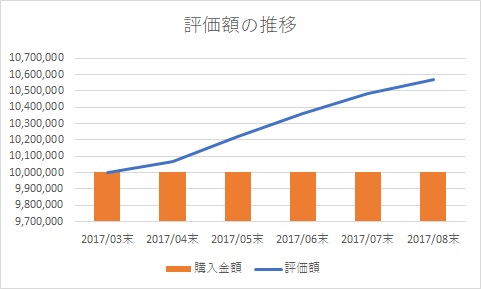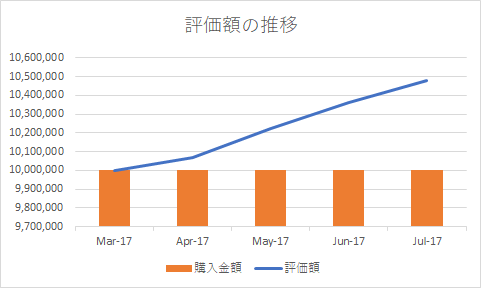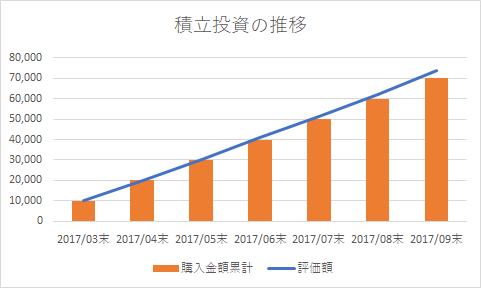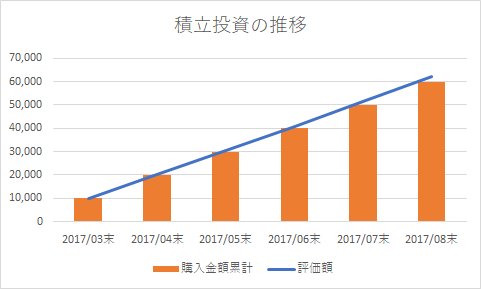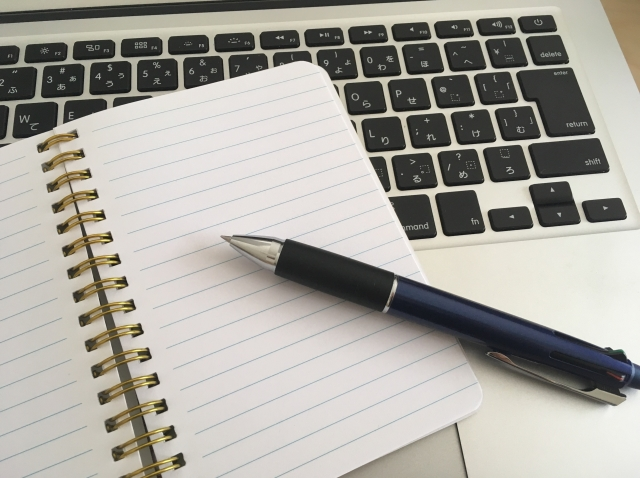2017/03/30

2017/5/17 日経新聞に、投信、根強い「分配信仰」、金融庁長官が批判で自粛でも・・という記事がありました。
金融行政方針 平成28事務年度によると今年度の金融庁は、日本人の家計資産の大半が預貯金で資産のリターンが低いこと、投資リテラシーが低く成功体験がない、ことを課題とし、少額・長期・積立による国民の安定的な資産形成、を施策として挙げています(4P)。
この観点からすると記事にあるように、
金融庁の森長官は「毎月分配では(長期投資に適した)複利効果が得られない」と販売手法の見直しを迫ってきた、というのは当然のことでしょう。積立NISAや確定拠出年金は税制優遇も含め、この目的にはかなっていますね。
一方、高齢者の個人は、分配金で元本を取り崩しているのは知っているが、資産を殖やし子供に相続するより今の生活水準を維持する方が大事、ともあります。退職金などを取崩し年金の不足分を補う、というニーズがある方も多いでしょう。
両社の言い分ともに一理ありますよね。最も違和感があるのは、
本業が苦しい地銀などは、毎月分配の投信販売に依存する金融機関が多い、という部分ですね。地域の金融機関が破たんをしたら困りますが、だからと言って地域の顧客の資産運用の不利益の上に成り立っているようでは釈然としない方も多いのではないでしょうか?
この記事にもあるように、また当サイトでも取崩しのシミュレーションを掲載していますが、年代や保有資産によって適した商品は変わるのは当然ですが、
取崩し=分配型投信、で良いか? ということだと思います。
取崩しをするための手段は、分配型投信以外にも
ETFの分配金を受取る
元本を一部解約する
などの選択肢があります。
複数の選択肢から自分に合った方法を選べる、
複数の選択肢を提示して、それぞれの特徴を整理して判断の手伝いをしてくれる、
ようになると良いと思いますがいかがでしょうか?